
はじめに|メダカ×ビオトープの魅力とは
近年、手軽に始められる自然飼育として人気を集めているのが「メダカのビオトープ」です。
屋外に設置した睡蓮鉢やプラ舟などで、自然に近い環境の中でメダカを飼育するスタイルは、見た目にも癒され、飼育の難易度も比較的低めです。特に初心者でも取り組みやすく、気軽に水辺のある暮らしを楽しめる点が大きな魅力です。
メダカは日本の在来種であり、四季のある日本の屋外環境に適応して生きてきた魚です。そのため、水温変化にも強く、繁殖も容易。設備もシンプルに済むため、「アクアリウムは難しそう…」という人にとっての“入り口”として、ビオトープは非常におすすめのスタイルです。
さらにビオトープは、単なる観賞用にとどまらず、生きたエコシステムの観察ができる楽しみもあります。水草が光合成で酸素を出し、微生物がゴミを分解し、メダカがその水の中で泳ぐ…まるで小さな自然が目の前にあるような感覚です。
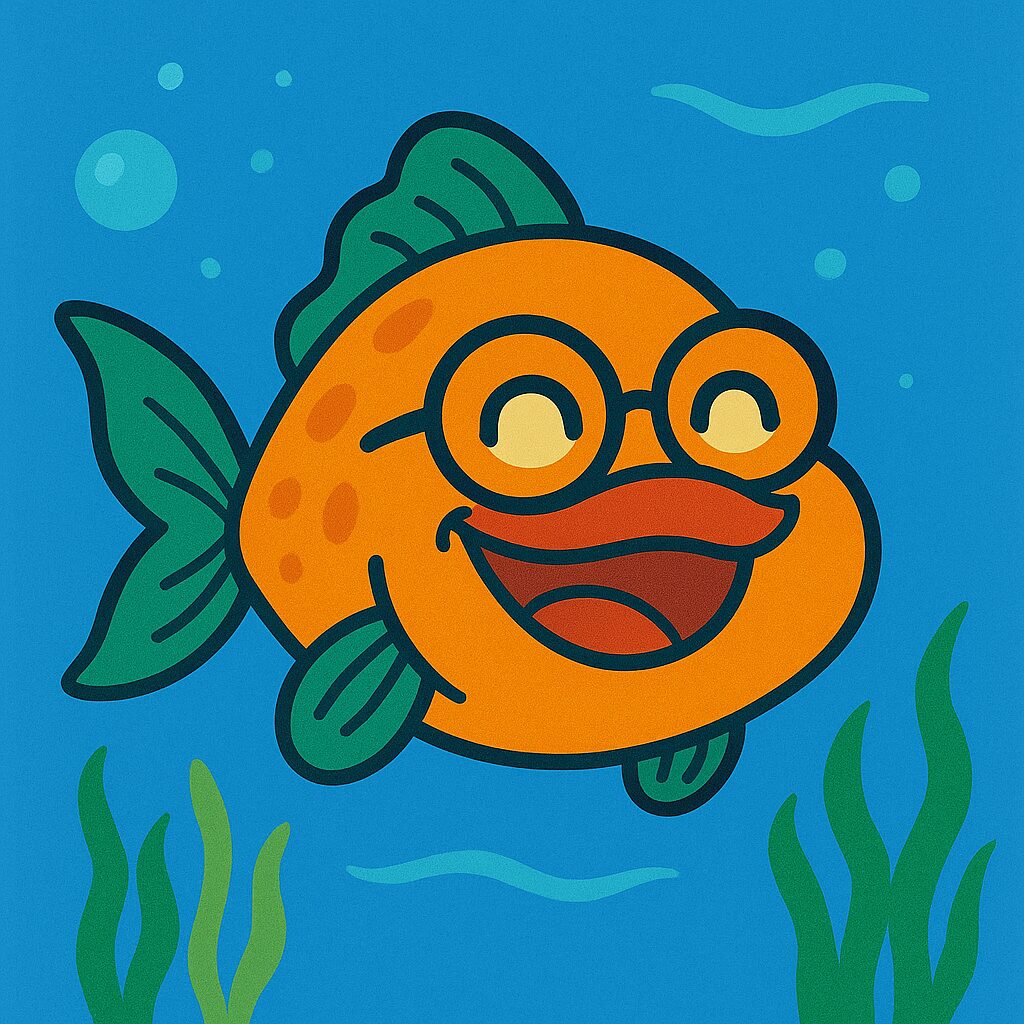
ビオトープってね、“生き物たちの暮らす場所”っていう意味なんだ〜!ただの水槽と違って、自然のバランスを活かした飼育ができるのがポイントなんだよ〜!
また、都市部のマンションやベランダでも設置できるのもポイント。サイズの小さな睡蓮鉢ひとつからでも始められるため、スペースに制限がある方でもチャレンジできます。
本記事では、そんな**「メダカのビオトープ」**の魅力を最大限に引き出すために、環境づくりからトラブル対策、繁殖方法やおすすめ品種までを詳しく解説していきます。
これからメダカを飼ってみたい人も、すでに室内水槽を持っていて新しい飼育スタイルに挑戦したい人も、ぜひ参考にしてみてください。
メダカにビオトープが向いている理由
ビオトープと聞くと「本当に魚が元気に暮らせるの?」と心配になる方も多いかもしれません。
ですが、メダカはビオトープ飼育に非常に適した魚種です。
その理由は、メダカが本来日本の自然環境で生きてきた在来種であることに深く関係しています。

1. 温度変化に強く屋外飼育に適応できる
メダカは寒暖差に強く、ヒーターなしでも飼育が可能です。春から秋にかけては屋外でも元気に泳ぎ、冬場には底の方でじっとして越冬します。特に関東以南の温暖な地域であれば、特別な加温設備を使わずとも一年を通じて屋外での飼育が可能です。

ビオトープは自然のままが基本だから、ヒーターがなくても過ごせるメダカはとっても向いてるんだ〜!でも、寒冷地の人はちょっと工夫が必要かもだよ〜
2. 繁殖が容易で自然な増殖が期待できる
ビオトープでは、水草や浮草の根っこに卵を産みつけることで自然繁殖も可能です。条件が整えば、親メダカが卵を産み、それが孵化し、稚魚が育つというサイクルが屋外でも自然に起こります。人工的な手助けがなくても命の連鎖を楽しめるのは、ビオトープならではの魅力です。
3. 食性が広く自然の餌も活用できる
メダカは雑食性で、水中の微生物や藻類、ボウフラ(蚊の幼虫)なども食べてくれます。そのため、屋外ビオトープでは人工餌だけに頼らず、自然発生した生き餌も重要な栄養源となります。こうした点も、ビオトープの中でうまく自然と共生できる理由です。
4. 小型で飼育スペースを選ばない
体長は2〜4cm程度と非常に小さく、睡蓮鉢や浅めのプラ船でも十分に飼育が可能です。アロワナや金魚のように広いスペースや強い濾過が必要ということもありません。ビオトープをベランダや玄関先に設置しても、コンパクトに楽しむことができます。
5. 品種が豊富で見た目も楽しめる
近年では観賞用に品種改良されたメダカも多く登場しており、幹之(みゆき)メダカ、楊貴妃、三色メダカ、ラメ系などの色彩豊かな種類が選べます。ナチュラルな水辺にカラフルな魚たちが泳ぐ光景は、観賞価値としても高く、ビオトープの風景を華やかに彩ってくれます。
このように、メダカは自然環境との相性が良く、ビオトープという飼育スタイルと非常に親和性の高い魚種です。
ビオトープに必要な環境と基本設備
メダカのビオトープを始めるにあたっては、自然に近い環境を意識しながらも、最低限の設備や条件を整えることが重要です。
ここでは、ビオトープの立ち上げに必要な「容器」「設置場所」「底床」「水」「濾過・エアレーション」の観点から詳しく解説します。
容器の選び方|睡蓮鉢・プラ舟・発泡スチロール
ビオトープ用の容器として代表的なのが、陶器製の睡蓮鉢や黒いプラ舟(コンテナ)、そして断熱性の高い発泡スチロール箱です。それぞれの特徴は以下の通りです。
| 容器の種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 睡蓮鉢 | 見た目が美しく和風の雰囲気に合う | 重くて割れやすい |
| プラ舟(黒) | 軽くて安価、水温が上がりやすい | 夏場は高温に注意 |
| 発泡スチロール | 保温性が高く冬越しに強い | 見た目が簡素で劣化しやすい |
初心者におすすめなのは、黒いプラ舟(40〜60L程度)です。コスパが良く、設置やメンテナンスもしやすいので失敗が少ない選択です。

容器の色は黒がいいってよく言われるけど、それは光の吸収率が高くて水温が上がりやすいからなんだ〜!でも夏は日陰に置く工夫が必要だよ〜
設置場所|日当たりと風通しのバランス
メダカの健康や水草の光合成のためにも、日当たりの良い場所に置くのが基本です。
ただし、直射日光が長時間当たりすぎると水温が上がりすぎたり、コケの繁殖を促す原因にもなるので注意が必要です。
理想は「午前中に日が当たり、午後からは半日陰になる場所」です。
風通しが悪いと水面にゴミや虫が溜まりやすくなるため、ある程度風が通る場所も意識しましょう。
底床(そこゆか)の素材|ソイル?砂利?
底に敷く素材としては、以下のような選択肢があります。
- 赤玉土:多孔質でバクテリアが住みやすく、コストも安い。崩れやすいので静かに扱う。
- 川砂・砂利:自然な見た目で掃除しやすい。ややバクテリア定着は弱い。
- ソイル:水質を弱酸性に保つ働きがあるが、屋外では崩れやすく不向きなことも。
初心者には中粒の赤玉土や丸みのある川砂がおすすめです。清掃しやすく、メダカの採卵時にも根がからみにくいため実用性も高いです。
水は水道水でOK?カルキ抜きは必須
ビオトープに使う水は、基本的には水道水で構いませんが、カルキ(塩素)抜きは必ず行いましょう。
市販の中和剤(ハイポやコントラコロラインなど)を使用するか、バケツに1日ほど汲み置きしておく方法でもOKです。
また、初期立ち上げ時はいきなり魚を入れず、水を張って2〜3日おいてから導入すると環境が安定しやすくなります。
濾過・エアレーションは必要?
多くのビオトープでは、あえてフィルターやエアポンプを使わない自然派スタイルが一般的です。
ただし、メダカの数が多い場合や夏場で水温が上がり酸素が少なくなる時は、スポンジフィルターやソーラーエアポンプを補助的に使うと安定します。

“無濾過・無機器”って聞くと心配になるかもだけど、水草やバクテリアがうまく働いてくれれば、自然のろ過が機能するんだ〜!でも過密飼育は避けようね〜
このように、ビオトープでは「自然に近い環境をつくる」ことが第一。
しっかりと準備すれば、機材に頼らずとも安定した飼育が可能です。次は、ビオトープの見た目を大きく左右する「水草・浮草・レイアウトの選び方」について解説していきます。
水草・浮草・レイアウトの選び方と役割
メダカのビオトープにおいて、水草や浮草は単なる「見た目の装飾」ではありません。
実は、水質の浄化・酸素の供給・産卵床としての役割など、生態系を安定させる重要な要素です。
ここでは、ビオトープに適した水草・浮草の種類と、それぞれの役割を詳しく見ていきましょう。
水草の役割とは?ただの飾りじゃない!
水草には大きく分けて、以下のような役割があります:
- 酸素を供給する(光合成)
- 水質を安定させる(硝酸塩・アンモニアの吸収)
- 隠れ家や産卵床として使える
- コケやアオミドロの発生を抑える(日光を遮る)
ビオトープではフィルターがないことも多いため、水草による自然のバランス調整がとても重要になります。

ビオトープは“バクテリア×水草×浮草”の三角関係が大事なんだよ〜!このバランスが崩れると、水がにごったり、メダカが弱ったりすることもあるんだ〜
おすすめの水草と浮草の種類
アナカリス(オオカナダモ)

初心者に最もおすすめ。安価で入手しやすく、育成も簡単。根を張らなくても使えるため、沈めるだけでOK。産卵床としても優秀。
ホテイアオイ(浮草)

浮かべるだけでOKな水草。根がよく伸びてメダカの隠れ家・産卵場所になる。強い日差しを遮って水温上昇を防ぐ効果も。ただし、増えすぎに注意。
マツモ

根を張らず、沈めるだけで使える沈水植物。水中で酸素を供給しつつ、コケ対策にも効果あり。繁殖も早い。
ドワーフフロッグビット(浮草)

ビオトープにおしゃれな雰囲気を出してくれる小型の浮草。光を遮りすぎないため、他の水草と共存しやすい。
ミリオフィラム、ウォーターバコパなど
見た目が華やかで、環境に馴染めば長期育成も可能。ただし、真夏の直射日光で枯れることがあるため注意。
レイアウトのコツ|美しさと機能性を両立
ビオトープでは、「見た目」も大事ですが、それ以上に「生態系の機能が成り立つ配置」が重要です。以下のポイントを意識しましょう。
- 背の高い水草やホテイアオイを後方に、低い草や石を前景に
- 浮草で水面を覆いすぎると光が足りなくなるため、1/3程度を目安に
- 流木や石を使って立体感を出すと、メダカの隠れ家や休憩場所になる
水草やレイアウト素材は、「デザインの一部」でもあり、「生き物のための構造」でもあります。バランスを取ることが長期安定のカギです。
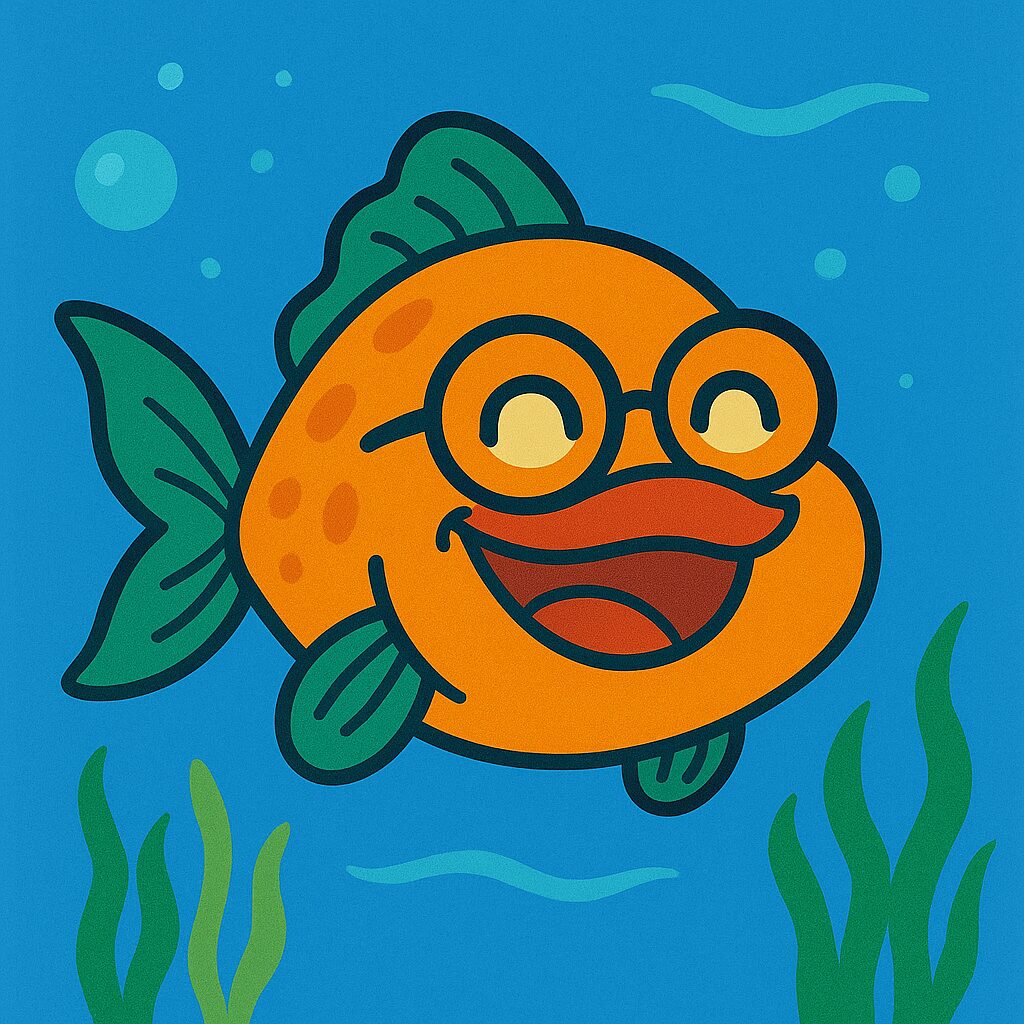
メダカは強い流れよりも、ゆるやかで落ち着ける空間が好きなんだ〜!だから、水草や石で“静かなゾーン”を作ってあげると、とってもリラックスしてくれるよ〜
メダカの導入手順と水合わせ方法
ビオトープの立ち上げが完了したら、いよいよメダカをお迎えする段階です。
ですが、「ただ水に放てばいい」というわけではありません。
水温や水質の急な変化は、メダカにとって大きなストレスとなり、導入直後の死亡リスクを高める原因にもなります。
そのため、「水合わせ」と呼ばれるステップを丁寧に行うことがとても重要です。
導入前に確認したい3つのポイント
- カルキ抜き済みの水を使用しているか
- 容器の水温が安定しているか(20〜28℃が理想)
- 直射日光下での作業を避けられるか
この状態が整っていれば、メダカを導入しても環境ショックを受けにくくなります。
水合わせの具体的な手順
以下の手順で、ショップや通販で購入したメダカを丁寧に水合わせしましょう。
① 袋ごと水面に浮かべて温度を合わせる(約20〜30分)
メダカが入った袋をそのままビオトープ容器の水面に浮かべ、袋の中と外の水温をゆっくり合わせます。
このとき、直射日光が強いと温度が上がりすぎて逆効果になるため、なるべく日陰で行います。
② 袋を開け、少しずつ容器の水を加える(30分〜1時間)
袋の口を開け、5分おきにビオトープの水を少しずつ(50〜100mlほど)袋の中に足していきます。
これを繰り返しながら、袋の水の半分〜2/3程度が容器の水に入れ替わった状態を目安にします。
③ ゆっくりとメダカを容器に放す
水合わせが完了したら、袋の水をなるべく入れないようにして、メダカだけをネットや手でやさしくビオトープに移します。
導入後は驚いて底に沈むこともありますが、数時間で落ち着いて泳ぎ出すのが一般的です。

“いきなり水に放しちゃった!”ってよくある失敗なんだけど、これがけっこう危ないんだよ〜。メダカは繊細だから、じっくり時間をかけて慣らしてあげてね〜
導入後の注意点
- 餌はすぐに与えない(1日休ませるのがベスト)
- 様子を見る時間を確保する(泳ぎ方や群れの動きに異常がないか)
- 天敵や飛び出し防止を確認する(特に浅めの容器は注意)
また、導入から1週間程度は水質がやや不安定になりやすいため、浮草の追加や水草の量を調整して様子を見ると良いでしょう。
メダカの繁殖を狙うなら?産卵・稚魚育成のコツ
ビオトープでのメダカ飼育の魅力のひとつが、自然繁殖による命の循環を身近に感じられることです。
条件が整えば、メダカは驚くほど簡単に卵を産み、次世代を残してくれます。
ただし、「放っておくだけで増える」というわけではありません。
繁殖を成功させるには、産卵の条件、稚魚の隔離方法、育成のコツを理解する必要があります。

産卵の条件|日照・水温・餌がカギ
メダカが産卵を行うためには、以下の条件が揃っていることが重要です:
- 日照時間が12時間以上
- 水温が20〜28℃程度
- 栄養価の高い餌をしっかり与えている
特に春〜初夏にかけては自然光が安定しており、ビオトープでの繁殖には最適な季節です。
メスは、条件が整うと1日に数粒〜20粒ほどの卵を体にくっつけたまま泳ぎ、数時間後に水草や浮草の根などに産みつけます。
産卵床として使える水草・アイテム
繁殖を狙うなら、**メダカが卵を産みやすい「産卵床」**をあらかじめ用意しておくと効率的です。おすすめは:
- ホテイアオイの根:自然な形で卵を産みつける
- アナカリス、マツモ:産卵床兼、隠れ家にもなる
- 人工の産卵床(毛糸やスポンジ素材):卵の回収がしやすく掃除も簡単

ホテイアオイの根っこはね、ふわふわしててメダカも安心して卵を産めるんだ〜!でも増えすぎたら光を遮っちゃうから、ときどき整理しようね〜
卵の回収と隔離|稚魚の食べられ対策
メダカの卵や稚魚は親魚に食べられてしまうことがよくあります。自然繁殖を観察したい場合でも、生存率を上げるには隔離が効果的です。
おすすめの方法:
- 産卵床ごと別容器に移す
- 浮きケース(隔離ネット)に稚魚だけ移す
- 発泡スチロール箱で簡易育成容器を作る
屋外であれば、日当たりの良い場所で静かに管理するのがポイント。直射日光や水温上昇には注意が必要です。
稚魚の育成|餌と環境管理のコツ
孵化したばかりの稚魚(針子)は非常に小さく、成魚とは全く違う飼育条件になります。
餌は何を与える?
- 最初の1週間:グリーンウォーター、稚魚用パウダー餌
- 2週目以降:すり潰した人工餌、ゾウリムシ、ブラインシュリンプ(あれば)
市販の「メダカのベビーフード」など、稚魚専用の微粒子餌も豊富に出ています。
水質はどう保つ?
- 底に汚れが溜まらないよう、スポイトで吸い出す
- 1日おきに1/4程度の水換え(カルキ抜き済みの水を使用)
- 強い水流やエアレーションは控える
このように、メダカの繁殖と稚魚の育成にはコツが必要ですが、命の循環を自分の手で見守れる体験はとても貴重です。

稚魚は“水がきれいすぎても、汚れすぎても”ダメなんだ〜!ちょっと難しいけど、ゆるやかなバランスが大事だよ〜
実際に起こりやすいトラブルとその対処法
ビオトープ飼育は自然に近い環境を楽しめる反面、人の目が届きにくい屋外だからこそ起こりやすいトラブルもあります。
特に初心者のうちは「気づいたときには手遅れだった…」という事例も少なくありません。
ここでは、実際によくあるトラブルとその対策方法を具体的に紹介します。
トラブル①|水温の急上昇・急低下
夏の猛暑や冬の寒波によって水温が大きく変化すると、メダカが弱ったり死亡するリスクが高まります。
【対策】
- 夏:容器を日陰に移動、すだれや遮光ネットで直射日光をカット
- 冬:発泡スチロール容器や断熱材を活用し、落ち葉やフタで保温
- 一気に温度を変えないよう、自然な調整を心がける

メダカは丈夫って言われるけど、急な温度変化はニガテなんだ〜。“ジワジワ”が合言葉だよ〜
トラブル②|鳥や猫に狙われる
ビオトープは屋外にあるため、サギ・カラス・猫などにとって“メダカのごちそうコーナー”になってしまうこともあります。
【対策】
- 容器の上にネットや金網をかける
- 浮草や水草で隠れ場所を作る
- 目立たない場所に設置する
透明な容器や水面が開けすぎていると狙われやすいため、**「水面を1/3以上浮草で覆う」**のも効果的です。
トラブル③|ボウフラの発生
エアレーションや水流のないビオトープでは、蚊が卵を産み、ボウフラが大量発生することもあります。
【対策】
- メダカ自体がボウフラを餌として食べてくれる
- 水面を浮草や水草で覆って蚊の産卵を防ぐ
- 水の停滞が激しい場合はエアーポンプや軽い水流を導入
稚魚水槽など、メダカがいない容器では定期的に水を換えるか、エアレーションを設置しましょう。
トラブル④|藻・アオミドロの異常発生
日当たりが良すぎると、水の中でコケ(藻類)が大繁殖して見た目が悪くなるだけでなく、水質悪化や酸素不足の原因になります。
【対策】
- 日照時間を調整(すだれ、遮光ネットなど)
- 浮草で光量をコントロール
- ミナミヌマエビや貝類を導入(ただし過密はNG)
特にアオミドロは水草に絡みつく厄介な存在。発生したら手で取り除き、換水と遮光でコントロールします。
トラブル⑤|水質悪化とアンモニア中毒
屋外であるがゆえにゴミ・落ち葉・雨水などが入り込みやすく、水質が悪化しやすいのもビオトープの特徴です。
【対策】
- 落ち葉やゴミはこまめにすくう
- 餌の与えすぎに注意
- 雨が降った後は水の透明度と匂いを確認
- 必要に応じて部分換水(1/4程度)を行う

“自然まかせ”もいいけど、放置しすぎは禁物だよ〜!水の色やにおいの変化には敏感になろうね〜
このように、ビオトープならではのトラブルには“自然を読み取る力”が求められます。
でも慣れてくれば、「今日は水が澄んでるな」「少し水草が増えすぎたな」といった微調整が楽しくなるはずです。
冬越しのポイントと注意点
ビオトープでメダカを飼う際に不安に感じることのひとつが「冬をどう乗り切るか」という点です。
特に屋外での飼育では、水温が10℃を下回ることもあり、「ヒーターなしで本当に大丈夫?」と心配になる方も多いでしょう。
結論から言えば、メダカはヒーターなしでも冬越しが可能です。
ただし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、より安全に、負担の少ない越冬が可能になります。

メダカの冬眠と水温の関係
メダカは水温が15℃を下回ると活性が下がり、10℃前後になるとほとんど動かなくなります。
この状態が「冬眠」と呼ばれるもので、底のほうでじっとして冬をやり過ごします。
この間は餌を食べず、代謝も落ちているため、水質が安定していればそれほど手はかかりません。
冬越しに適した容器と設置場所
- 深さのある容器(25cm以上)を使用すると、水温の急変に強くなります。
- 地面に直接置くと冷えやすいため、断熱マットやすのこなどで底上げしましょう。
- 風通しの良すぎる場所よりも、建物の陰や壁際など、冷たい風を避けられる場所がおすすめです。

冬は“寒さ”よりも“急変”がこわいんだ〜!深さがあれば、水の中はけっこう穏やかなんだよ〜
落ち葉・氷・雨水の影響に注意
屋外では自然の影響をそのまま受けるため、次のような対策をしておきましょう。
- 落ち葉やごみはこまめに取り除く(腐敗して水質悪化の原因に)
- フタやすだれで軽く覆うと落ち葉や冷気の侵入を防げる
- 大雪や氷結が予想される場合は、ビニール温室の中に移すのも効果的
完全に凍結してしまうとメダカも危険なので、寒冷地では越冬用の対策をしっかりと施す必要があります。
冬場は餌やりを控えるのが基本
水温が10℃以下になると、メダカは餌をほとんど消化できません。
無理に餌を与えると、消化不良や水質悪化の原因になるため、基本的には与えない方が安全です。
水温が10℃以上ある暖かい日中に、様子を見て少量だけ与える程度で十分です。
冬越しが難しい地域では室内退避も検討
寒冷地(東北・北陸・北海道など)では、ビオトープの水が完全に凍るリスクが高いため、屋内での越冬が推奨されます。
- 発泡スチロール容器ごと室内に移動
- 小型のヒーター付き水槽に一時避難
- 屋内日当たりのよい窓際で簡易飼育もOK
ただし、室内に移すと日照や酸素供給が足りなくなることもあるため、水質管理に注意しましょう。
冬越しのコツは、「無理に手を出さないこと」と「水温・水質の急変を避けること」にあります。
自然なリズムを見守る気持ちで、春までゆっくりと付き合っていきましょう。
ビオトープにおすすめのメダカ品種
一口に「メダカ」といっても、その品種は数百種を超え、色・体型・模様・ヒレの形など多種多様です。
ビオトープでは、丈夫さ・日光映え・繁殖のしやすさを基準に選ぶと、より安定して飼育を楽しめます。
ここでは、見た目の美しさとビオトープ適性の両立ができるおすすめ品種を紹介します。
黒メダカ|自然派レイアウトとの相性抜群
最も原種に近いメダカ。体色が黒〜灰色で、水草や落ち葉とよく馴染み、自然志向のビオトープにマッチします。
暑さ・寒さに強く、繁殖力も高いため、初心者にもおすすめです。
- 日陰の水面でも視認性が高い
- 病気に強く、環境適応力も◎
楊貴妃メダカ|発色の良さで一番人気
オレンジ〜朱赤の体色が非常に美しい品種。
黒い容器や緑の水草と合わせると、映えるカラーで存在感抜群です。
- 屋外でも発色が落ちにくい
- 人気が高く、入手しやすい

楊貴妃メダカはね、まるで金魚みたいな色合いが魅力なんだ〜!ビオトープを華やかにしたい人にはぴったりだよ〜
幹之(みゆき)メダカ|光をまとったような美しさ
背中に青白く光る「光沢」があるのが特徴。屋外の自然光で見ると、まるで小さな光の粒が水面を泳いでいるようです。
- ラメの入り具合により、グレードがさまざま
- シンプルな容器でも上品な印象に
※日陰が多い場所ではやや発色が目立たないこともあるため、日照を意識したレイアウトが効果的です。
三色メダカ・紅白メダカ|変化を楽しむアートな魚
赤・白・黒などの模様が入り交じった品種。模様の出方が個体によって異なるため、まさに“育てる楽しみ”があるメダカです。
- 変化を楽しみたい中級者向け
- 落ち着いた環境で色が安定しやすい
小川ブラック・オーロラ系|シックで個性的な魅力
黒や深い青を基調にした品種は、シックで落ち着いた雰囲気のビオトープにマッチします。
特にオーロラ系は、角度や光によって体色が変化し、見るたびに表情が変わる面白さがあります。
品種を混ぜる時の注意点
異なる品種を混泳させると、繁殖時に交雑が起き、子どもの特徴が失われることがあります。
観賞用としての混泳は可能ですが、「純血を維持したい」場合は品種ごとに分けることをおすすめします。
また、成魚同士でも体格差が大きいとストレスの原因になるため、導入時のサイズも揃えると安全です。
このように、ビオトープの雰囲気や自分の好みに合わせてメダカを選ぶことで、飼育の満足度も大きく変わってきます。
次はいよいよ最後のまとめとして、ビオトープ飼育の魅力と今後のアクションについて振り返ります。
まとめ|自然と調和した飼育でメダカの魅力を最大限に
メダカのビオトープ飼育は、自然のサイクルを身近に感じながら、魚たちの生命力や繊細な行動をじっくり観察できる飼育スタイルです。
機械に頼らない“静かな水辺”の中で、四季の移ろいや水草の成長、メダカの繁殖など、日々の小さな変化を楽しむことができます。
本記事では、ビオトープにおける以下のポイントについて詳しく解説しました:
- メダカがビオトープに適している理由
- 容器や設置場所、水草の選び方
- メダカの導入手順と繁殖・育成のコツ
- よくあるトラブルとその対処法
- 季節ごとの注意点(特に冬越し)
- 飼育に向いたおすすめ品種
ビオトープは、見た目の癒しだけでなく、“小さな自然環境を育てる体験”そのものが魅力です。
だからこそ、最初の立ち上げから、日々の観察、そしてトラブル時の対処まで、自然の理を感じながら一歩ずつ付き合っていく姿勢が大切です。
ビオトープは決して難しいものではありません。
最初の一歩として、睡蓮鉢ひとつと数匹のメダカから始めてみませんか?
自然とともに暮らす楽しさを、ぜひ体験してみてください。

自然の中でメダカと暮らすって、なんだか心まで整ってくる感じがするよね〜!
のんびり眺めてるだけでも癒されるし、気づいたら季節の変化にも敏感になってたりして…!
ビオトープ、ほんとにおすすめだよ〜!


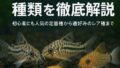
コメント